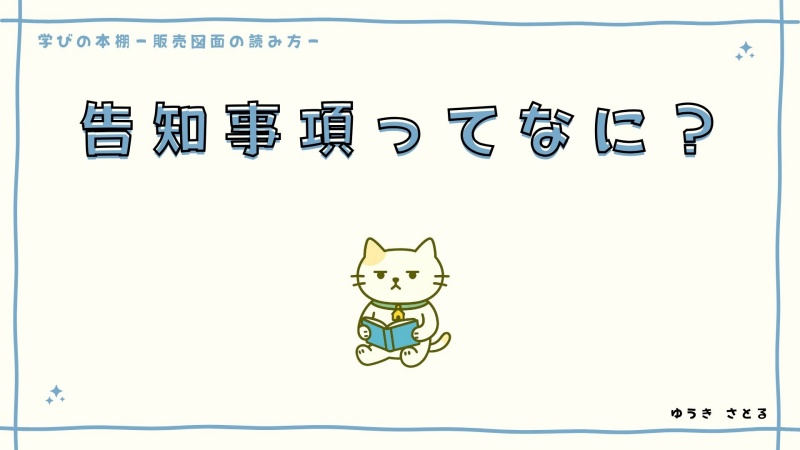家探しをしていると、販売図面の片隅に小さく書かれた
「※告知事項あり」
という文字を見かけることがあります。
はじめて住宅を探す方からすると、
-
「告知事項って何を意味してるの?」
-
「事故物件ってこと?」
- 「なんか怖いんだけど...」
と不安に思うかもしれません。
でも、しっかり意味を理解すれば、必要以上に怖がる必要はありません。
この記事では、「告知事項あり」の本当の意味と、確認すべきポイントをわかりやすく解説します。
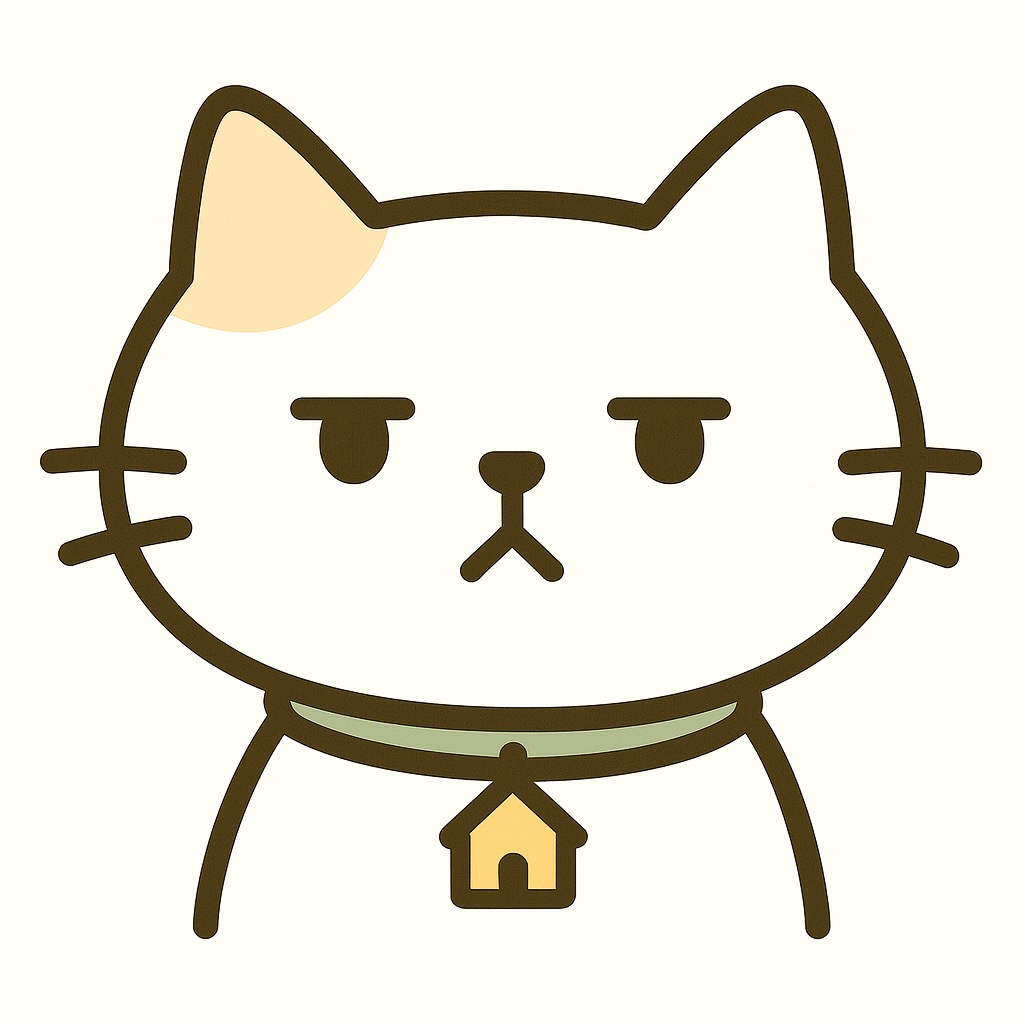

「告知事項あり」とは?
簡単に言うと…
🏠 買主が知っておくべき“特別な事情”がありますよ、という合図。
これは「宅地建物取引業法」に基づくルールで、
買う人に不利益になる可能性がある情報は伝えなければならないとされています。
図面では「申し伝え事項あり」「心理的瑕疵あり」と書かれることも。
よくある「告知事項」の例
実際に「告知事項あり」とされるケースはさまざまです👇
-
過去に自殺や孤独死、事件があった(いわゆる事故物件)
-
周囲で騒音・臭気・振動などの生活環境トラブルがある
-
近隣に反社会的勢力との関わりが疑われる建物がある
-
建物で火災が発生したことがある
-
所有者に関する事情(相続中、離婚協議中 など)
つまり、「心理的に影響を与える出来事」や「取引に関わる事情」がある場合に記載されることが多いです。
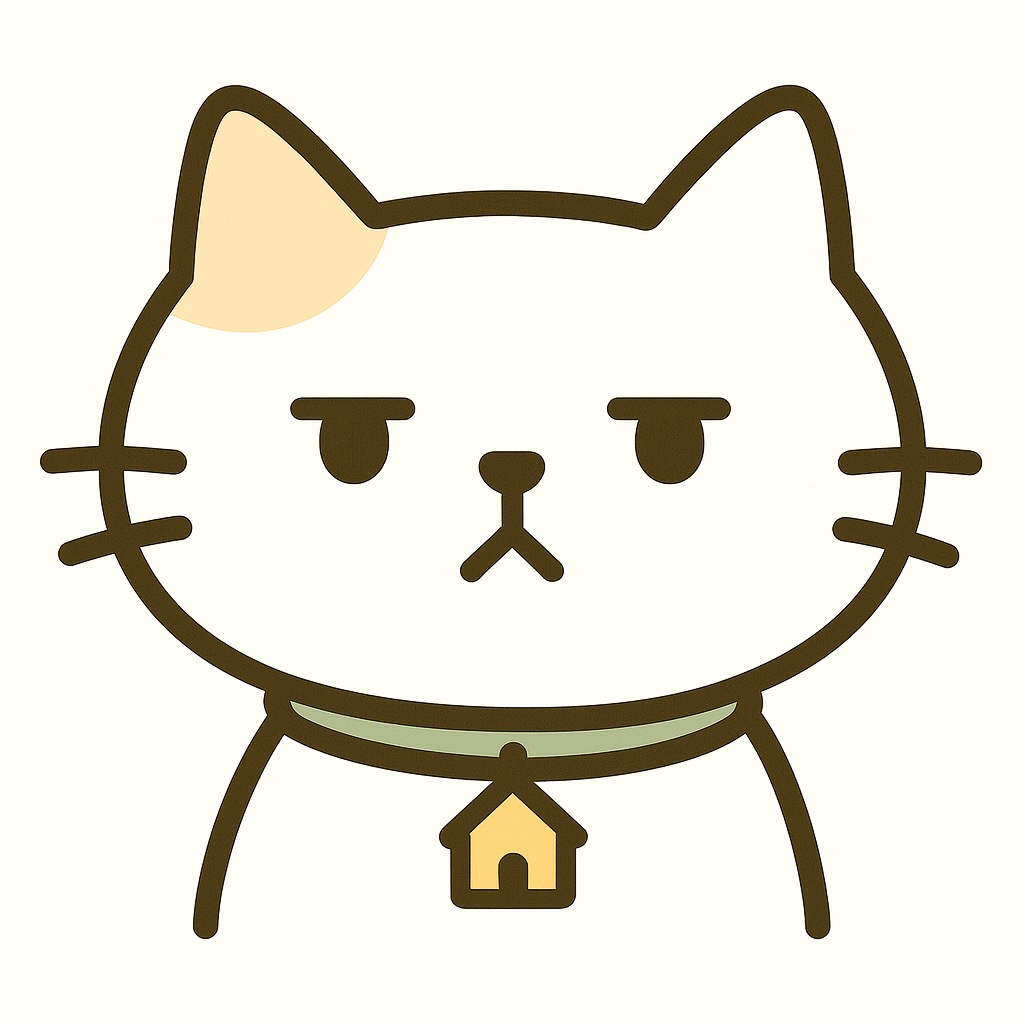
ていうか“隣が反社かも”って、一番イヤなんだけど。
ただ、“告知事項あり=事故物件”とは限らないってことです。

図面で見つけたらどうする?
販売図面で「告知事項あり」を見つけたら、まずは担当営業に確認してください。
💬 聞くべき質問はシンプルにこれです
「どんな内容の告知事項ですか?」
ポイントは、内容を確認してから判断すること。
「事故物件」とは限らない
実は、「告知事項あり」と書かれていても、必ずしも重たい事情とは限りません。
-
高齢者の看取り(自然死)
-
日常生活の中での事故(浴室での転倒など)
こういったケースも「告知事項あり」と表記されることがあります。
心理的な抵抗がなければ「特に問題なし」と判断する人も多いです。
逆に、自殺や事件などのケースでは心理的な影響が大きいため、しっかりと確認・納得したうえで判断する必要があります。
説明が不十分なことも
正直なところ、「告知事項あり」と伝えると物件価値が下がることがあります。
そのため、営業マンによっては…
-
説明を後回しにする
-
曖昧に表現する
-
メリットでごまかす
あってはならないことですが、こういうケースもゼロではありません。
内見の時には言わずに、いざ契約となった段階で話に出してくることも。。。
👉 だからこそ、販売図面の小さな文字を見落とさず、自分から確認することが大切です。
国交省のガイドライン(2021年)
以前は「どこまで告知すべきか」が曖昧でしたが、2021年に国土交通省が
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(国交相HP)
を公表し、基準が明確化されました。
✅ 告知が不要なケース(原則)
-
高齢者の自然死や病死(看取り)
-
日常生活の中での突発的事故(浴室での転倒など)
👉 こうしたものは「通常の生活で想定される」とされ、原則告知は不要です。
✅ 告知が必要なケース
-
自殺や他殺、事故死など心理的抵抗があると判断される死
-
火災や事件による死亡
-
発生から概ね3年以内のもの
- 特殊清掃が発生したようなケース
👉 「社会的関心が高く、購入判断に影響する出来事」は原則告知が必要です。
👇宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
国交相HP
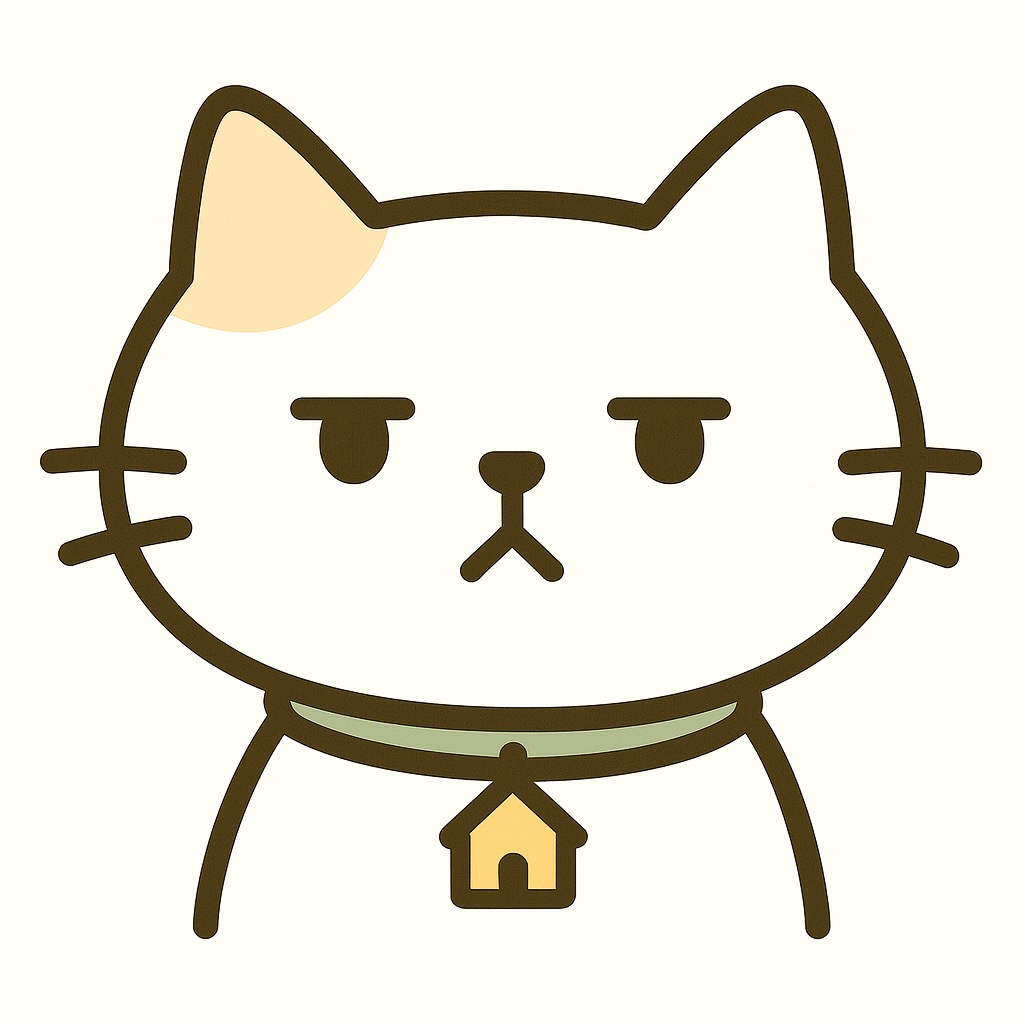
でもさ…“3年経ったらOK”って基準、ちょっと不思議じゃない?
でも最終的には“ご自身が納得できるかどうか”がいちばん大事だと思いますよ。

剛田さんからのアドバイス
「告知事項あり」と書かれていると、つい構えてしまうのは自然なことです。
でも大事なのは、内容を知ったうえで“ご自身とご家族の価値観”で判断することなんですよ。
-
軽微な事情なら「気にしない」もアリ
-
重大な事情なら「納得できなければやめる」でOK
-
怖がりすぎて候補を狭める必要はありません
私としては、国交省のガイドラインに外れているから伝えなくてもいい、ではなく、
一般常識から考えて気になる点は必ずお伝えすべきだと思っています。
事前に聞いていれば納得できることでも、あとから近所の人の噂で知ったら気分はよくないですからね。
結局のところ──
「告知事項あり」は 重要なサイン。
必ず担当者に内容を確認し、ガイドラインも参考にしながら、
最終的には“納得できるかどうか”で選ぶこと。
家は価格や立地だけではなく、背景も含めて安心できるかどうかが本当に大切なんです。
\ 無料LINE講座やってます /
📩営業ゼロ!自分のペースで学べる
10STEP『後悔しないマイホーム選び』
講座の詳細と登録方法はこちら👇
(※ボタンクリックでご案内ページに移動します)