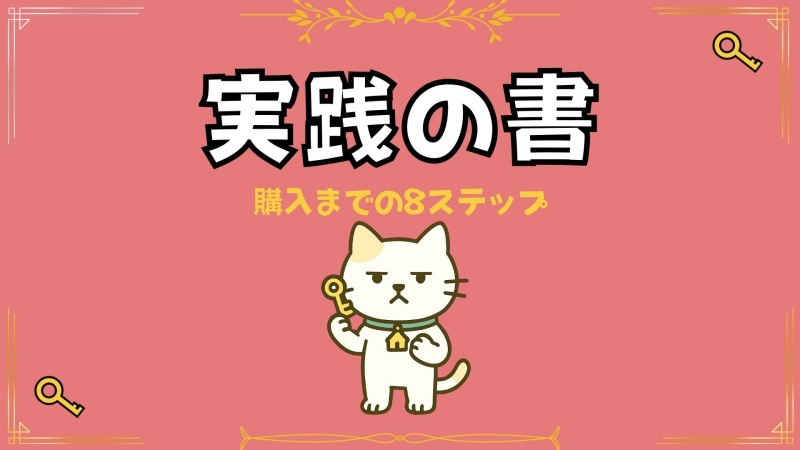こんにちは、不動産購入エージェントの結城さとるです。
この記事では、物件の内見から契約、そして引渡しまでの流れを8つのステップに分けて解説します。
⚠️ 注意点
この記事は「実戦編」です。読む前に、まずは「準備編|家探し前にやるべき10ステップ」を先に確認してください。
👉 後悔しないマイホーム選び【購入準備編】|家探し前にやるべき10ステップ
なぜなら ―
家探しは“準備が9割”。
資金計画や条件整理といった土台を整えていないまま進めても、途中で迷ったり、後悔する可能性が高くなるからです。
準備ができている方にとって、ここからの8ステップはまさに「実戦」。
そして実戦編では、準備編と違って 専門家の力を借りながら進めること が大切です。
それでは、内見から引渡しまでの流れを一緒に見ていきましょう。

目次
STEP1|実際にサポーターを選ぶ(担当者の見極め)
1. 担当者と出会うルート
家探しで担当者と出会う方法はいくつかあります。
- ポータルサイト経由(SUUMO・HOME’Sなど)
物件を問い合わせると、その会社の担当者から連絡がきます。ただし担当者は選べず、会社都合で割り当てられるのが難点です。 - 現地販売会・オープンハウス
建物や周辺環境を直接見られるのは大きなメリット。ですが、その場の雰囲気や営業トークに流されやすいので注意が必要です。 - 不動産エージェントを自分で指名
価値観や考え方が合いそうな人を、自分で探して選べます。ブログやYouTube、Xなどの発信から人柄を知れるのが強みです。
👉 この中でおすすめなのは 「不動産エージェントを自分で選ぶ」 方法です。
2. なぜエージェントなのか?
不動産エージェントは、会社のノルマや売上至上主義で動く営業担当とは立場が違います。
- 中立的な立場:物件を売り込むのではなく、サポートの結果として報酬を得るスタイル
- 寄り添い型:あなたの基準やペースに合わせて伴走してくれる
- 選択肢重視:会社の都合ではなく、あなたに合う選択肢を一緒に探してくれる
💡 だからこそ「担当者を自分で選べる」という点で、エージェントが安心なのです。
3. 会う前にできるリサーチ
最初から多くの人に会うのは大変。だからこそ、会う前のリサーチで候補を絞っておきましょう。
- 会社HP/スタッフ紹介:得意エリアやプロフィールを確認
- ブログ:物件紹介だけでなく「買い方」や「暮らし方」を発信しているか
- YouTube:話し方や雰囲気から人柄を直感的にイメージ
- X(旧Twitter):強引さより「暮らしに寄り添う」発信ができているか
- 口コミ(Googleレビュー等):実際に依頼した人の声をチェック
👉 この時点で候補を2〜3人に絞っておけば、無駄な労力が減ります。
4. 信頼できる担当者を見極めるポイント
実際に会ったときは、こんな点をチェックしましょう。
- レスポンスが早く誠実
- メリットもデメリットも伝えてくれる
- 契約を急かさない
- あなたの優先順位を理解して提案してくれる
- 希望エリアに詳しい(相場や周辺施設の知識)
- 「安心して話せる」と感じられるかどうか
5. NGサイン(信頼できない担当者)
- 「今日決めれば安くなります」と煽る
- 不都合な情報を曖昧にする
- 条件を聞かずに物件を押し付けてくる
- 質問に答えられず、はぐらかす
- ノルマや会社都合が透けて見える
- 得意エリアがなく知識不足を隠す
6. 担当者選びのコツ
理想は複数人と比較すること。
ただし大切なのは「違う」と思ったら、遠慮なく担当を変える勇気を持つことです。
一生に一度の大きな買い物だからこそ、
「なんか違うけどまあいいか」で妥協せず、
「この人なら安心できる」と思える相手を選びましょう。
まとめ
- 会う前にHP・ブログ・SNS・口コミでリサーチ
- 会ったら「理想像」と「NGサイン」で見極める
- 違和感があればすぐに担当を変えてOK
👉 家探しの満足度は、物件より「人」で決まります。
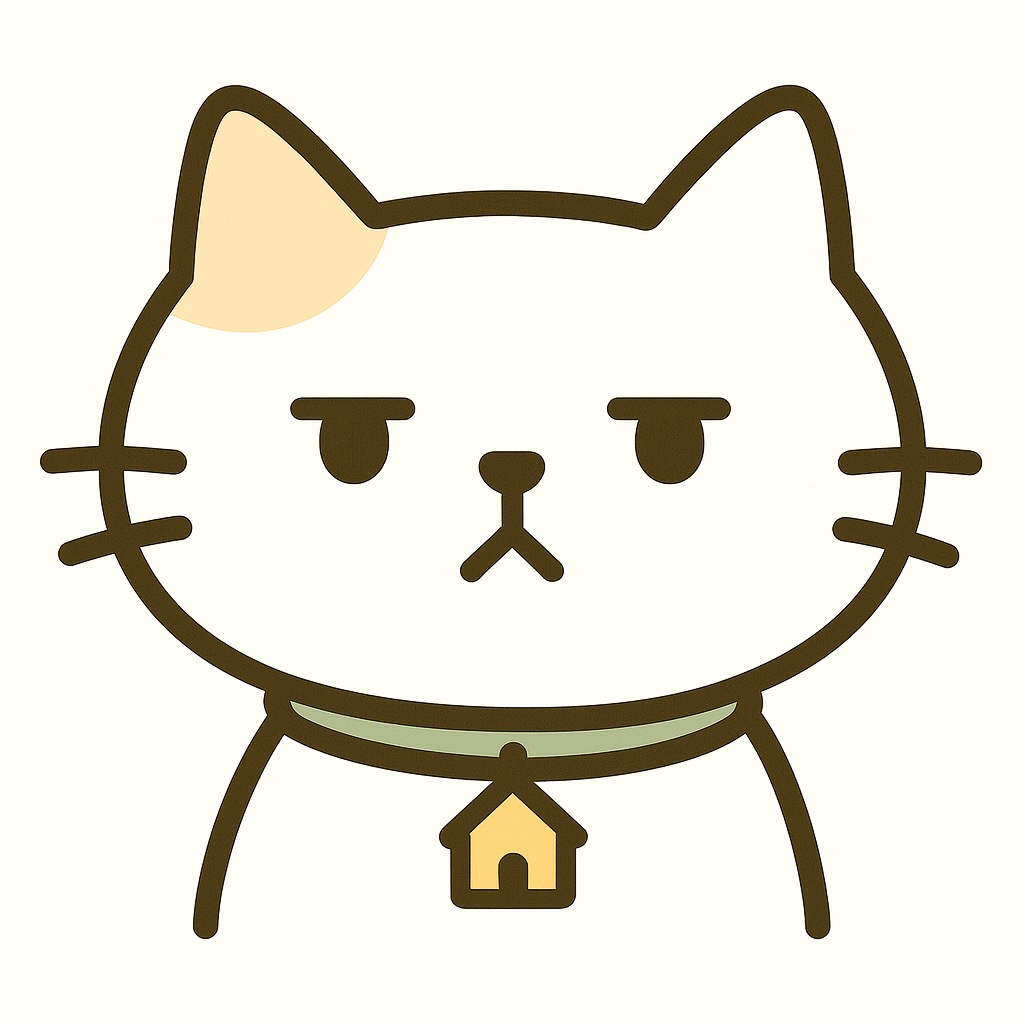

STEP2|住宅ローン事前審査(エージェント経由で)
1. なぜ今このタイミングで必要?
「事前審査=買える証明」です。
購入申込の際、この証明があるかどうかで交渉力も安心感も大きく変わります。
準備編で済ませた方は読み飛ばしてOK。まだの方は、このタイミングで必ず行いましょう。
2. エージェントを通すメリット
住宅ローンは自分でも銀行に行って申し込めますが、初めての人には複雑で分かりにくいことが多いです。
エージェントを通すと、こんなメリットがあります。
- 必要書類の準備をサポートしてくれる
- 複数の金融機関を比較してアドバイスしてくれる
- 「この銀行はこの属性に強い」など、現場の知識を持っている
- 手続きの流れを整理してくれるので、抜け漏れが減る
3. エージェントを通さずにやる場合(大変さの例)
自分で銀行に行く場合、こんな負担があります。
- 各銀行ごとに書類の書き方や必要資料が微妙に違う
- 金利や手数料、保証料などを自分で比較しなければならない
- 「どこが自分に合っているか」を判断する基準が分かりづらい
- 同時に複数行へ申し込むのが手間で、時間がかかる
💡 結果として「なんとなく一番最初に行った銀行」で決めてしまう人も少なくありません。
4. 事前審査に必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 健康保険証
- 源泉徴収票(給与所得者)または確定申告書(自営業者)
- 購入予定物件の資料(販売図面など)
👉 書類を集める段階からエージェントに相談すると、「どの書類がいつ必要か」を整理してもらえるので迷わず準備できます。
5. 金融機関の選び方
事前審査では「どこで借りるか」をある程度選ぶ必要があります。
- 金利の種類(固定か変動か)
- 保証料や事務手数料
- 団信(団体信用生命保険)の内容
金融機関によって条件は微妙に異なります。
👉 複数社に同時申込するのが基本で、その調整をしてくれるのもエージェントを通す大きなメリットです。
6. 注意点
- 事前審査は「通った=絶対借りられる」ではない(本審査が本番)
- 審査中に新しい借入やカードの使いすぎはNG
- 「借りられる額」ではなく、準備編で立てた資金計画を基準に判断する
まとめ
事前審査は購入プロセスのスタートライン。
エージェントなしでも可能ですが、手間やリスクが増えやすいです。
エージェントを通すことで、書類の抜け漏れや比較の手間を減らし、安心して進められます。
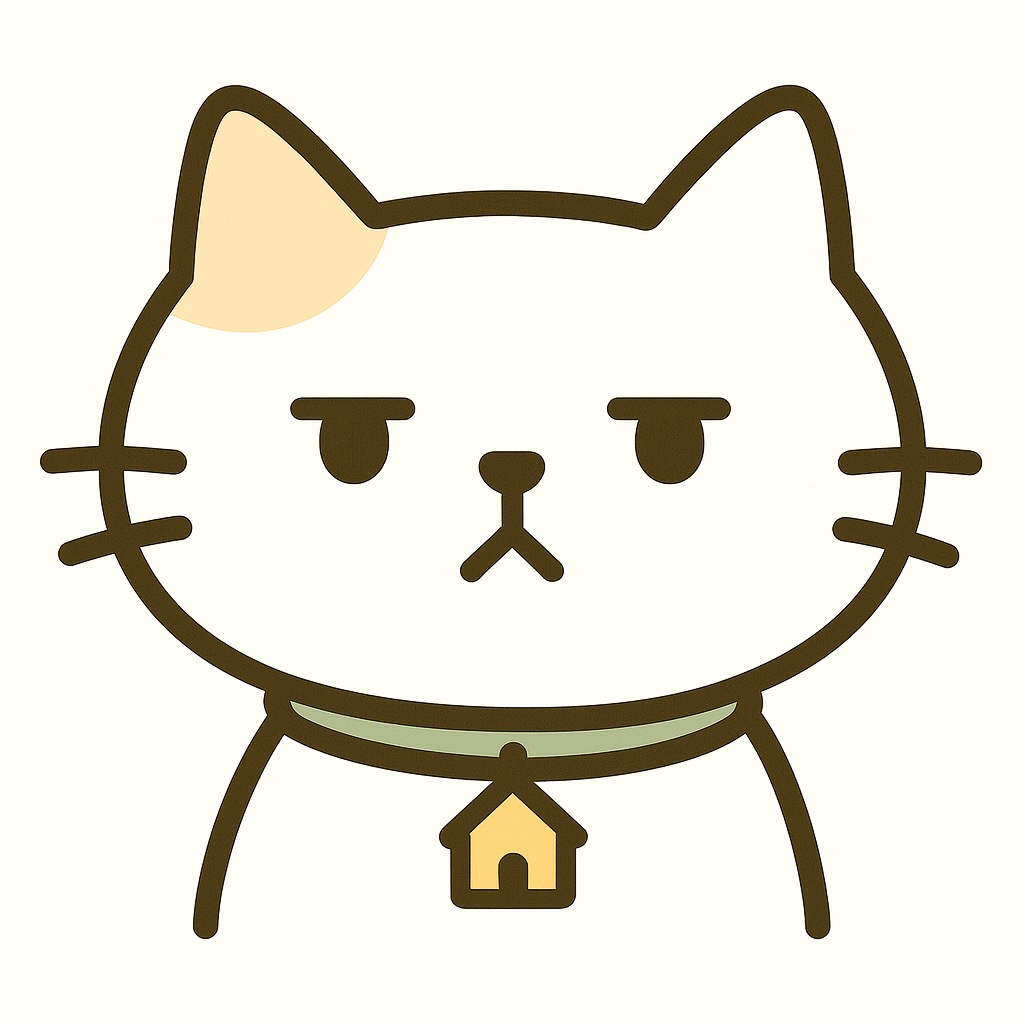

STEP3|内見と候補の絞り込み
1. まずは候補をしぼる
内見は「たくさん見ればいい」というものではありません。
実際には、見れば見るほど分からなくなり、決断できなくなる人が少なくありません。
- 「もっといいのが出るだろう」と思い続けて、何年も探し続けてしまう
- 物件見学が“趣味”になってしまい、購入の決断から遠ざかる
👉 だからこそ、準備編で整理した条件をもとに、候補は 3〜5件に絞り込む ことが大切です。
2. 内見前の下調べ
効率よく見るために、現地に行く前にある程度調べておきましょう。
- Googleマップやストリートビューで周辺環境を確認
- スーパー・病院・学校までの距離
- 駅までの道のりや交通量
- 間取りや設備を事前に目を通しておく
💡 下調べをしておけば、内見当日は「暮らしをイメージする」ことに集中できます。
3. 内見当日のチェックポイント
内見は “物件を見る”+“暮らしをイメージする” の両方を意識。
- 室内:日当たり、風通し、収納量、劣化の有無、コンセント位置
- 周辺:騒音や匂い、駐車スペース、近隣住人の雰囲気
- 道のり:駅までの安全性(夜道・坂道・交通量)
👉 写真や動画を撮っておくと、後で冷静に比較できます。
4. 内見迷子を避けるために
- 「もっといいものが出るかも…」と探し続けると、いつまでも決められません
- 新築のきれいさや雰囲気に流されて“即決”してしまうのも危険
💡 大切なのは、今ある物件の中から選び切ること。
見学した物件は必ず 優先順位をつけてリスト化 してください。
5. エージェントと一緒に見る意味
エージェントと内見に行くと、こんなメリットがあります。
- デメリットや修繕リスクを冷静に指摘してくれる
- 相場や資産価値の観点からコメントしてくれる
- 比較の視点を与えてくれるので「雰囲気」で流されにくい
まとめ
内見は「数をこなす」より「しぼって比較」することが大切です。
今ある物件を冷静に比べ、必ず優先順位をつける。
その積み重ねが、後悔しない決断につながります。
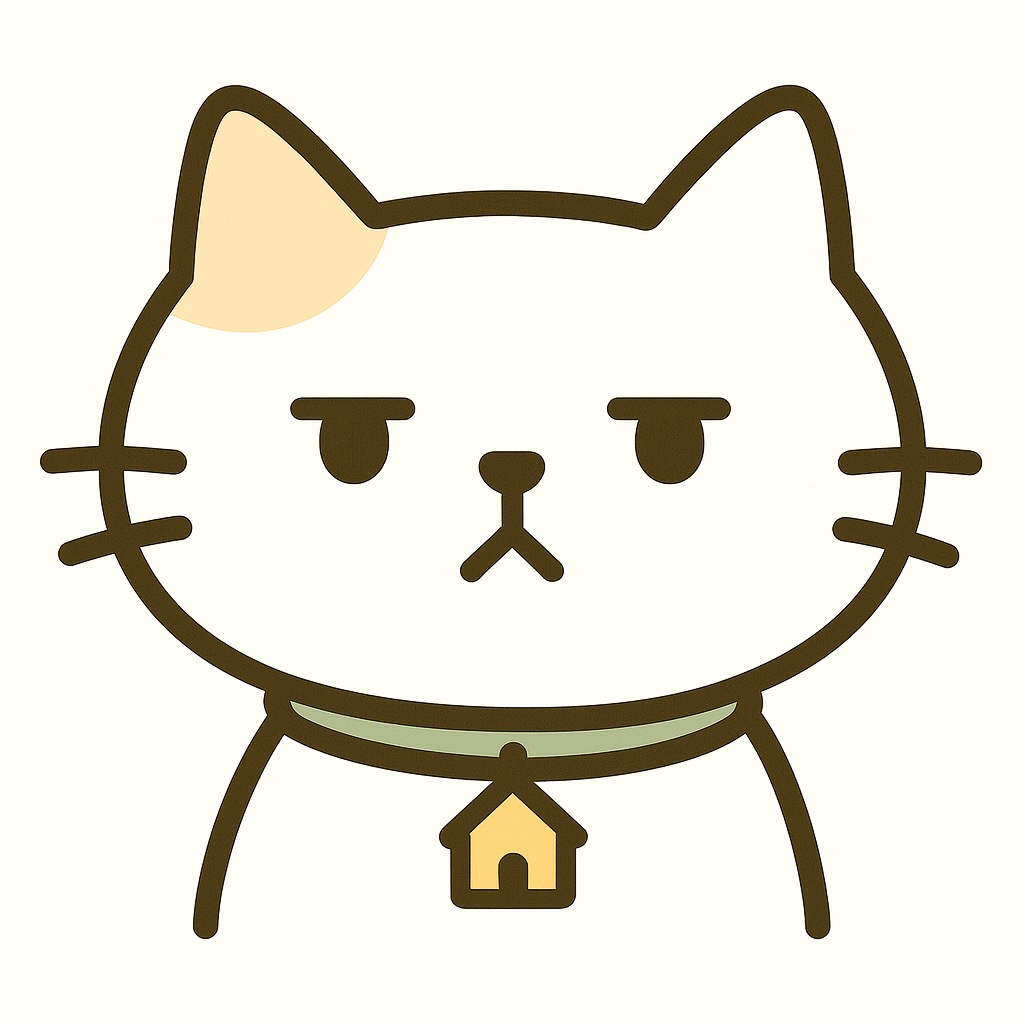

STEP4|購入申込と条件交渉
1. 購入申込とは?
気に入った物件が見つかったら、「購入申込書(買付証明)」を提出します。
これは「この条件で購入したい」という意思表示であり、まだ正式な契約ではありません。
👉 この段階で「価格」「引渡し時期」「設備」など、条件の調整を行うことができます。
2. 交渉できる項目
- 価格(指値)
- 引渡し時期
- 設備の残置(エアコンや照明など)
- 修繕やリフォーム費用の負担
💡 値下げ交渉は一般的ですが、基本は“出ている金額で購入する”前提です。
「できたらラッキー」くらいの心構えで臨みましょう。
3. 交渉の進め方
- 「〇〇万円にしてください」ではなく、**「こういう理由があるからこの金額で買いたい」**と理由を示す
- 理由づけは必ずエージェントと相談して整理する
- 相場はあくまで参考。売主にとって重要なのは「売却事情」や「時期」
4. エージェントと交渉するメリット
交渉は、プロであるエージェントを通すことで結果が変わることがあります。
- その物件や時期の特徴から「交渉できそうか、できなさそうか」を事前に教えてくれる
- 場合によっては、売主側に事前にコンタクトして“ジャブ”を打ってくれる
👉 「値下げ余地はありそうですか?」とさりげなく確認し、交渉の余地があるかを探る - 適切な温度感で交渉を進めてくれるので、売主の心象を悪くしにくい
💡 自分ひとりで強気に交渉するよりも、売主との関係性を知っているエージェントに任せた方が安全でスムーズです。
5. 注意すべきこと
- 交渉は「できることもあれば、できないこともある」
- あらかじめ自分のスタンスを決めておく
- 条件が通らなければ絶対に買わないのか
- 少しでも近づけばOKなのか
- 条件が通らなくても「買いたい物件」なのか
👉 ここを整理しておかないと、交渉がこじれたときに迷走してしまいます。
まとめ
購入申込は「この条件で買いたい」という意思表示。
交渉はできることもあれば、できないこともあります。
エージェントと相談しながら、「この物件をどうしても欲しいのか」「条件次第なのか」を明確にした上で臨みましょう。
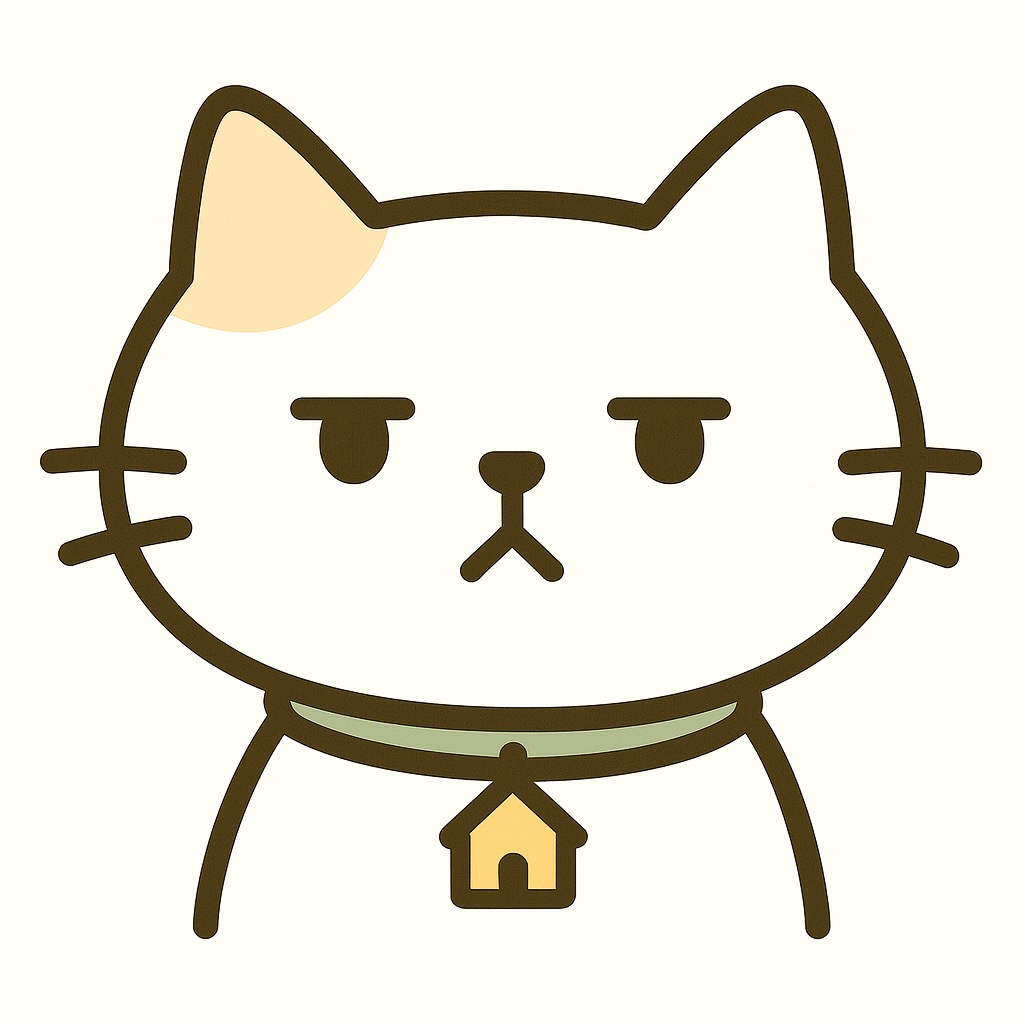

STEP5|重要事項説明と売買契約
1. 重要事項説明(重説)とは?
契約前に、宅地建物取引士が「物件や取引条件の大切なこと」を説明する手続きです。
専門用語が多くて難しく感じるかもしれませんが、ここで内容を理解・納得した上で契約に進むのがルールです。
2. 実務の流れ
重説と売買契約は法律上は別々の手続きですが、実務では 同じ場で続けて行われるのが一般的 です。
所要時間はおおむね 2時間30分〜3時間。
- 重要事項説明(1時間〜1時間30分)
- 売買契約の読み合わせ・署名捺印(1時間前後)
- 手付金の支払い
👉 その日をもって「正式に買う」ことが決まります。
3. 重説・契約で確認すべきこと
長時間の手続きで疲れてしまいがちですが、次の点はしっかりチェックしてください。
- 境界・権利関係に問題がないか
- 用途地域・防火地域など法的制限は大丈夫か
- 建ぺい率・容積率が違法になっていないか
- 契約解除の条件(手付金放棄で解約できるか 等)
- 支払いスケジュール(手付金・中間金・残代金の流れ)
💡 疑問に思ったら「この部分をもう一度説明していただけますか?」でOK。
4. よくある落とし穴
- 専門用語だらけで「とりあえずハンコ」を押してしまう
- 契約解除条件を理解しないまま進めてトラブルになる
- 支払いスケジュールを確認せず、資金繰りに焦る
👉 完璧に理解する必要はありません。
分からない点を聞く勇気を持つことが一番大事です。
5. エージェントの役割
エージェントがいれば、心強いサポートが得られます。
- 重説や契約の内容を生活者目線で補足してくれる
- 契約書に不自然な点がないか事前に確認してくれる
- 支払いスケジュールや手付金の金額を事前に整理してくれる
まとめ
STEP5は「不動産購入の正式スタートライン」。
重説と契約は別手続きですが、実務では続けて行われ、2時間半〜3時間ほどかかります。
長丁場でも気になる点は必ず質問し、エージェントに補足してもらいながら安心して署名捺印に進みましょう。
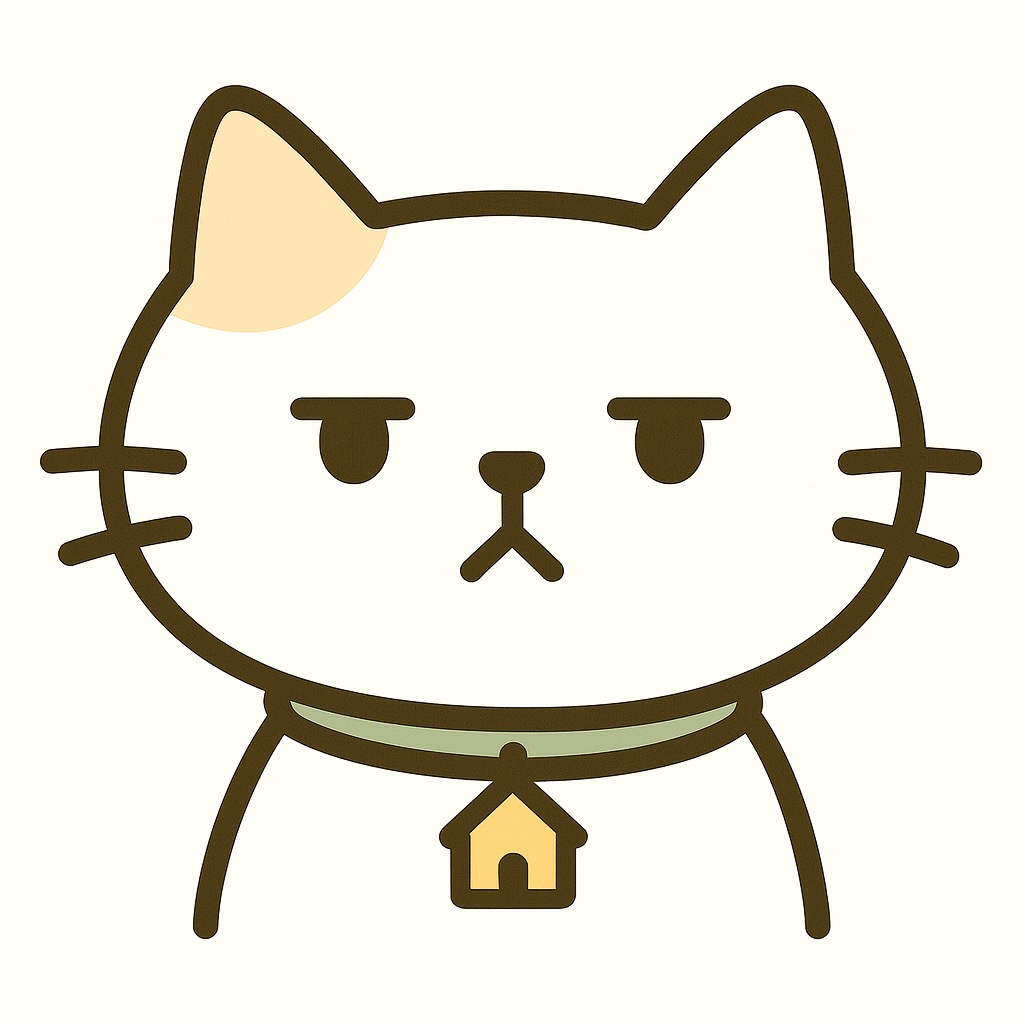

STEP6|住宅ローン本審査
1. 本審査とは?
事前審査は「お金を借りられる可能性があるか」をざっくり確認する段階でした。
一方で本審査は、金融機関が 購入者の返済能力 と 物件の担保価値 を詳しくチェックする本番の審査です。
👉 事前審査に通っていれば、ほとんどの場合は本審査も問題なく通ります。
ただし 条件が変わると結果が変わる ため要注意です。
2. 本審査で必要な書類
- 住民票
- 印鑑証明書(実印)
- 収入証明(源泉徴収票や課税証明書など)
- 売買契約書の写し
- 物件資料(登記簿謄本、図面など)
💡 書類に不備があると審査が止まります。エージェントに段取りを確認しながら揃えておくと安心です。
3. 要注意!条件が変わると結果も変わる
事前審査に通っていても、本審査で落ちることがあります。主な原因は「条件の変化」です。
- 新たにローン(車・ショッピングローン等)を組んでしまった
- クレジットカードのリボ払いやキャッシングを利用してしまった
- 転職や収入の大きな変化があった
👉 本審査に入ったら、できるだけ 生活を普段通りに保つこと が大切です。
4. 審査期間の目安
本審査には おおむね1〜2週間 かかります。
金融機関や時期によってはさらに時間がかかることもあるため、引渡しスケジュールを逆算して余裕をもって申し込みましょう。
5. エージェントの役割
- 書類の準備をサポートしてくれる
- 金融機関とのやり取りを代行してくれる
- 審査に時間がかかる場合、売主側に説明してスケジュールを調整してくれる
- 万が一のために、別の銀行の選択肢を用意してくれる
まとめ
- 本審査は「購入者」と「物件」を詳しく審査する段階
- 事前審査に通っていればほとんど問題ないが、条件変化に注意
- 審査期間は1〜2週間が目安。余裕をもってスケジュール管理を
- エージェントの助けを借りることで、手続きや調整をスムーズに進められる
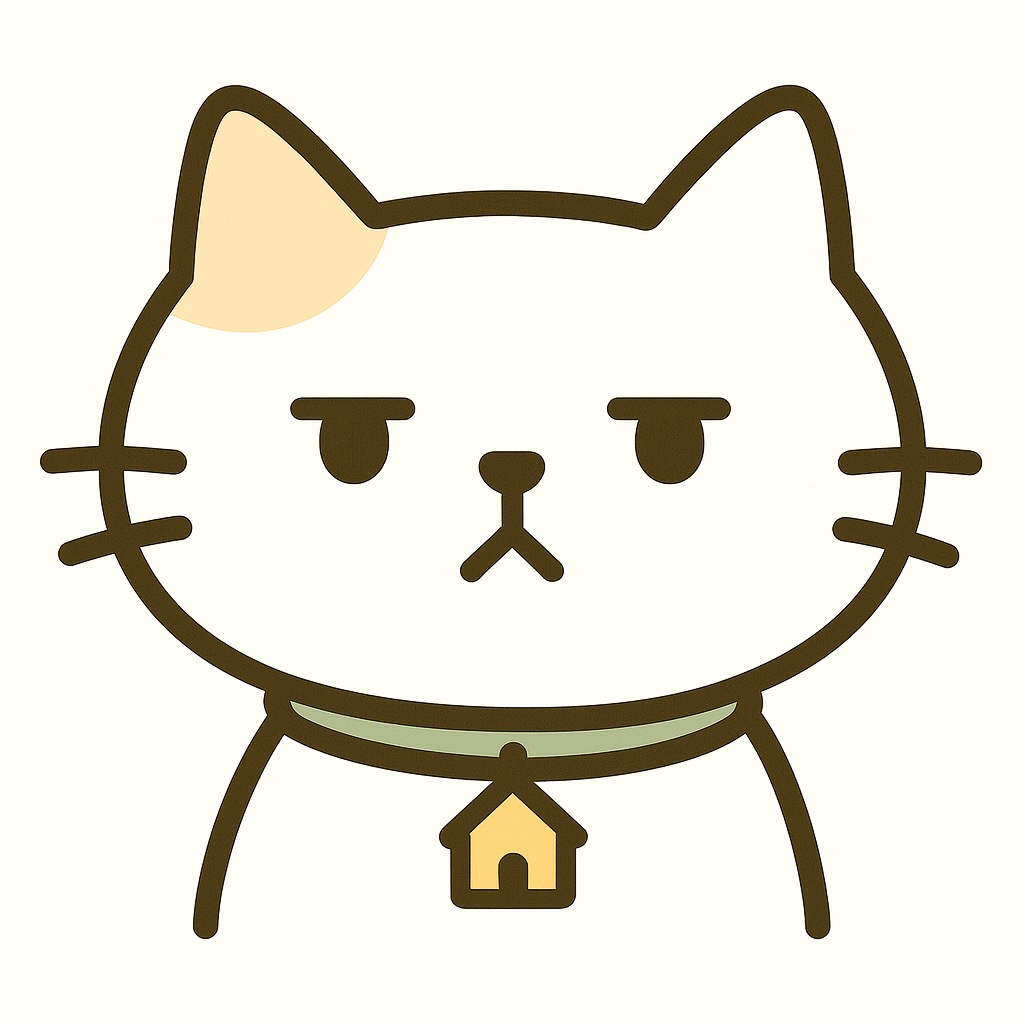

STEP7|金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)
1. 金銭消費貸借契約とは?
本審査をクリアしたら、金融機関と正式に「お金を借りる契約」を結びます。
この契約で初めて、
- 借入額
- 金利タイプ(固定・変動など)
- 返済期間・返済方法
- 繰上げ返済のルール
などが確定します。
👉 この段階の決定が、これから30年以上の返済生活を左右します。
2. 契約時に必要なもの
- 実印
- 印鑑証明書
- 住民票
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 売買契約書の写し
- 頭金や諸費用の入金証明(必要に応じて)
💡 銀行の窓口で1〜2時間程度かかるのが一般的です。
3. 金利タイプの比較表
|
金利タイプ |
メリット |
デメリット |
向いている人 |
|
固定金利 |
返済額がずっと変わらない安心感 |
初期金利が高め |
長期的な安定を重視する人 |
|
変動金利 |
初期金利が低く、当初の返済額が抑えられる |
金利上昇リスクあり |
将来収入アップを見込む人/短期で返済計画の人 |
|
固定期間選択型 |
一定期間は金利が固定される安心感+変動より低めの金利 |
期間終了後に金利が上がる可能性 |
10年以内に繰上げ返済や住み替えを検討している人 |
👉 どれを選ぶかは「家庭のライフプラン」と「リスク許容度」で決まります。
4. 契約で確認すべきこと
- 繰上げ返済条件(手数料や手続き方法)
- 団体信用生命保険(団信)の補償内容や特約の有無
- 保証料・事務手数料が総返済額にどれくらい影響するか
💡 契約書に書いてあること=将来のルール。不安があれば必ず確認を。
5. エージェントのサポート
エージェントは銀行の契約には同席できない場合もありますが、事前相談は有効です。
- 自分のライフプランに合う金利タイプを一緒に検討できる
- 団信の選び方や返済期間の考え方を整理してもらえる
- 契約書の難しい部分をあらかじめ解説してもらえる
まとめ
STEP7は「住宅ローンの条件を最終決定する日」。
金利タイプや返済方法など、今後の暮らしを左右するポイントが多いので、事前にエージェントや金融機関担当に相談し、不安を残さずに契約を結びましょう。
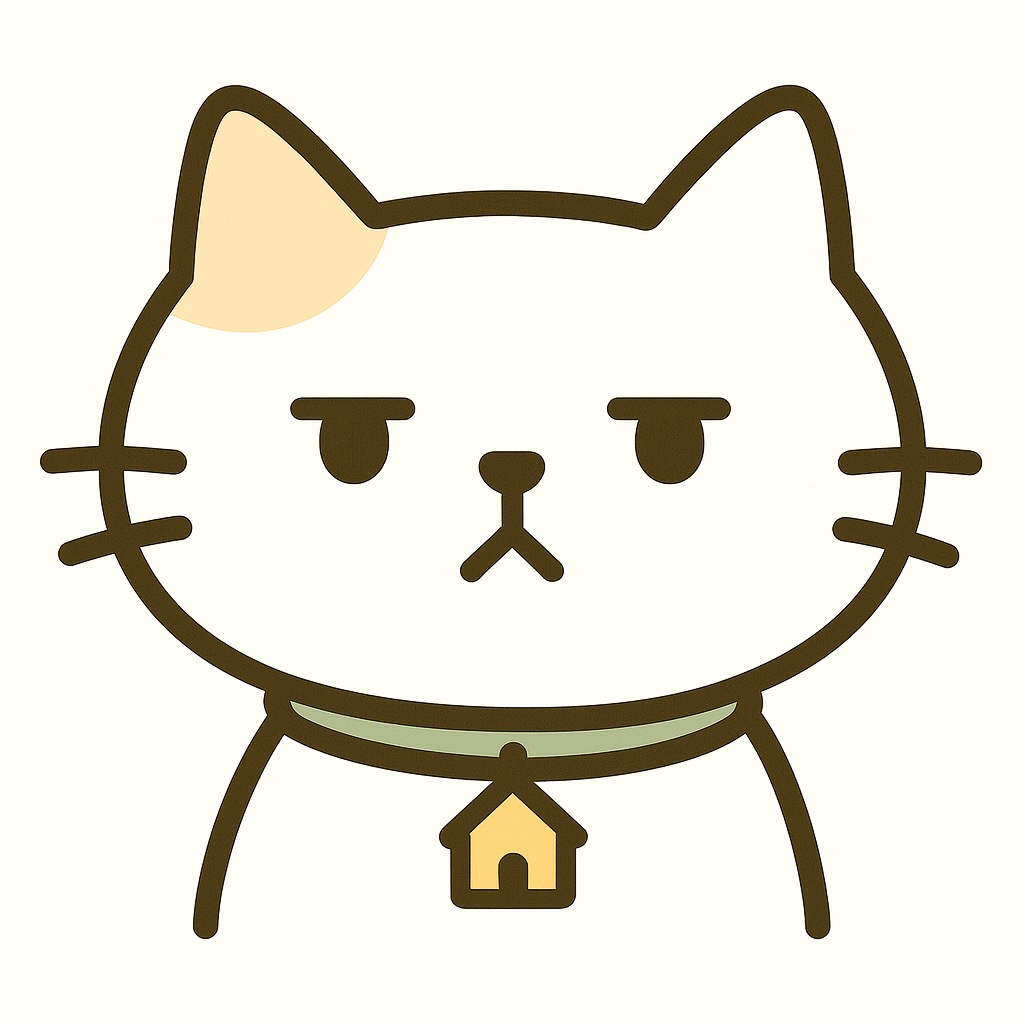

STEP8|決済・引渡し
1. 決済・引渡しとは?
いよいよ物件の所有権があなたに移り、正式に「自分の家」になる日です。
この日をもって、売主に残代金を支払い、司法書士の立会いのもと登記を行い、鍵を受け取ります。
👉 契約から完成物件で約1か月後が目安。新築未完成物件の場合は、建物完成に合わせて行われます。
2. 当日の流れ(一般的なケース)
- 金融機関に集合(買主・売主・司法書士・仲介会社が同席)
- 残代金の振込・確認
- 登記申請(司法書士が手続き)
- 鍵の受け渡し
- 諸費用の清算(固定資産税の精算など)
💡 所要時間は2〜3時間程度。午前中から始めて昼過ぎに終わるパターンが多いです。
3. 当日の持ち物チェック
- 実印
- 印鑑証明書
- 通帳・銀行印
- 残代金(振込用)
- 諸費用(司法書士費用・仲介手数料など)
👉 不備があると決済自体ができないので、事前にエージェントや銀行担当と確認しておきましょう。
4. 引渡し前にやっておくこと
- 公共料金(電気・ガス・水道)の契約切替手続き
- 住民票の移動・住所変更の準備
- 引越し業者の手配
- ネット回線や郵便物転送の手続き
💡 鍵を受け取った瞬間から、固定資産税や光熱費の責任は買主に移ります。
5. 注意点
- 残代金が金融機関から予定通り振り込まれないと決済が成立しない
- 鍵を受け取る前に、室内の最終確認(傷や設備不良がないか)をしておく
- 新築の場合は施主検査を、リフォーム物件の場合は完了確認を必ず実施
6. エージェントの役割
- 決済当日の流れを段取りしてくれる
- 必要書類や持ち物を事前にリストアップしてくれる
- トラブルがあった場合、金融機関や売主との間に入って調整してくれる
まとめ
決済・引渡しは、購入プロセスのゴールであり新生活のスタートライン。
当日の流れや持ち物を事前に確認し、エージェントのサポートを受けながら安心して臨みましょう。
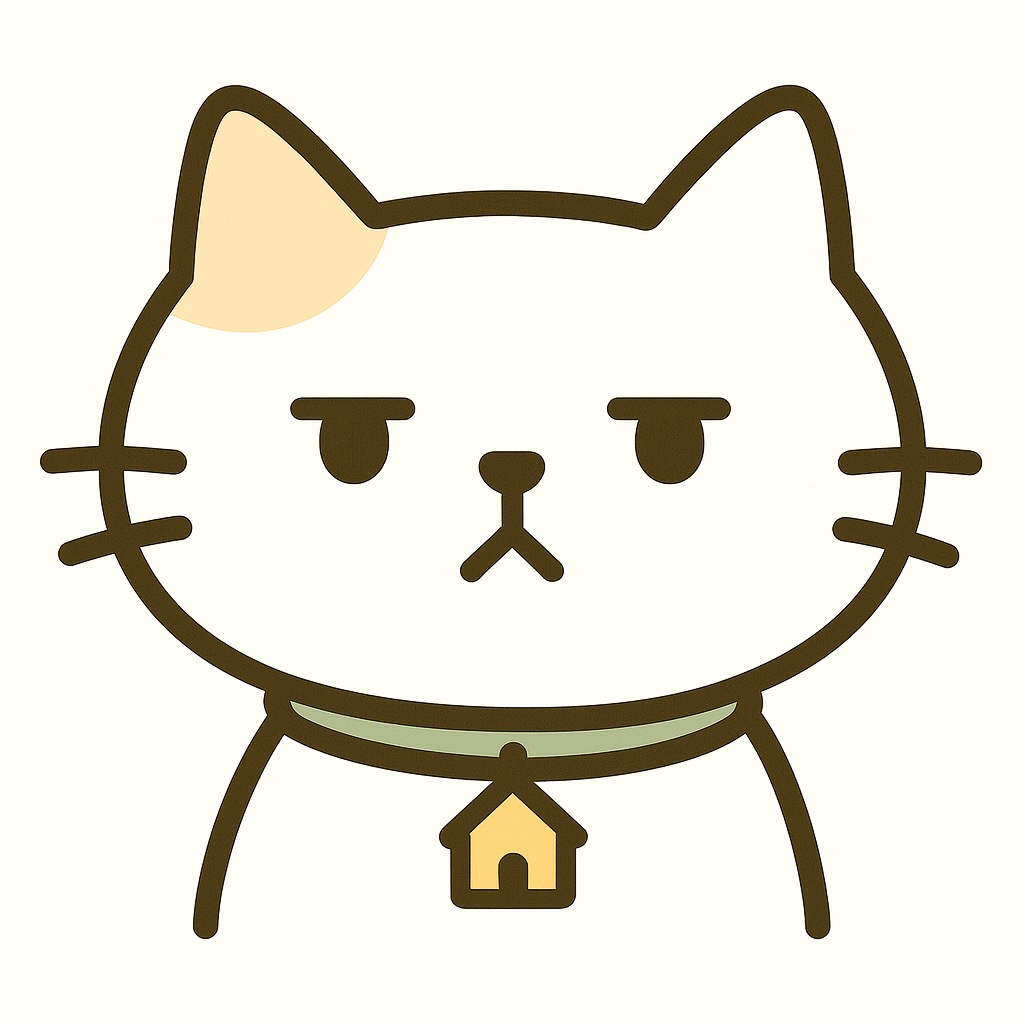

以上が、内見から引渡しまでの8ステップでした。
- STEP1で「誰と進めるか」を決め
- STEP2で事前審査を行い
- STEP3〜STEP8で実際の申込・契約・ローン・決済へと進んでいく
こうして見ると、不動産購入は思った以上に手続きが多く、専門的な知識も必要になります。
でも大丈夫。準備編で基準を固め、実戦編で信頼できるエージェントと二人三脚で進めれば、不安は大幅に減らせます。
よくある疑問:契約から引渡しまでどのくらい?
契約したらすぐに住める、と思っている方も多いですが、実際には一定の時間がかかります。
- 完成済みの新築や空室の中古 → 契約から約1か月
- 売主が居住中の物件 → 売主の次の住まい探しが必要なため、1〜3か月かかることも
- 建築中の新築 → 建物完成後の引渡し
✅ 入居時期に希望がある場合は、必ず契約前に確認しておくことが大切です。
💡 無料LINE講座でまずは家選びの準備を整えましょう。
登録後に「相談希望」と送っていただければ、個別アドバイスも可能です。
\ 無料LINE講座やってます /
📩営業ゼロ!自分のペースで学べる
10STEP『後悔しないマイホーム選び』
講座の詳細と登録方法はこちら👇
(※ボタンクリックでご案内ページに移動します)